名古屋大学 未来材料・システム研究所教授 山本 真義 氏
「テスラ3」をバラして分かったニッポン製造業の勝ち筋
多くの国が2030年を目処に内燃機関の廃止や規制を掲げる中、自動車のEV化は今後ますます加速していく。世界の自動車産業をリードしてきた日本メーカーも、EVでは少々遅れを取っている感は否めない。
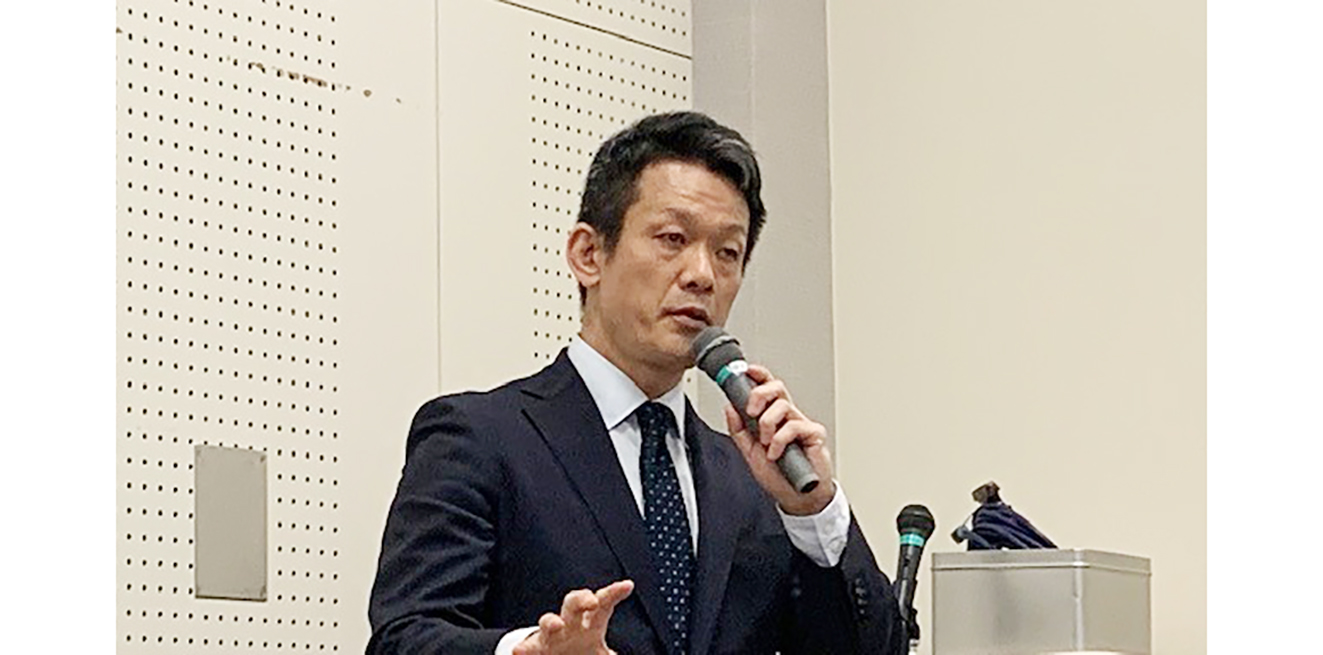
これまで日本メーカーは自社ですべてをまかなう一気通貫型のモノづくりを得意としてきたが、これが大きな足かせとなっている。一番のデメリットとなっているのがスピード感の欠如である。日本式のクルマ作りは、設計からや安全性の確保など開発からリリースまでにかかる期間がおよそ5年か。だが中国ではこれを2年でやってしまう。
ひと昔前に、日本ではPDCAを回すことを重要視していたが、いまや回しているうちに他国から新しいプロダクトがどんどん出てきてしまう。
テスラのエントリークラスセダン「モデル3」を分解してみると、世界初のSiCパワー半導体を使用した三相インバータが搭載されている。これはインバータの小型軽量化に大きく貢献しており、車体におけるサスペンション方式の自由度の獲得にも繋がっている。実はこの技術、日本の大手自動車メーカーが20年以上前から取り組んできたもので、テスラが世に出す前にほぼ完成していた技術でもある。こうした基幹部品を作るスピード感においても、日本メーカーは他国の後塵を拝してしまっているのが現状である。
では、このスピード感を上げていくためには何が必要なのか。必要不可欠なのは、完成車メーカーと取り巻く企業の連携強化であろう。これまでサプライヤーの多くは上位メーカーからの「指示待ち」で供給を行ってきた。だが、これからはサプライヤーが完成車メーカーの視点に立ったモノづくり、すなわち「クルマ作りをより深く知った上での開発力」が重要になる。
独・ボッシュを例に挙げると、これまではデンソーのような立ち位置のサプライヤーに過ぎなかった。だが、現在は完成車が作れるレベルのエンジニアを大量に抱えており、いまではBMWやメルセデスなどといった大手完成車メーカーをコントロールできる立場になりつつある。
このようにサプライヤーが完成車の設計開発を意識したモノづくりを行えば、スピード感が上がることはもちろん、完成車メーカーも開発リソースを別の分野に振り分けることができる。実際にメルセデスはクルマを通じた社会貢献を視野に入れた開発にも注力しはじめている。
とはいえ、これまで数十年間に渡って日本の自動車産業で行われてきた慣習を変えるのは容易ではない。だが、いまやらなければ日本の自動車産業はますます衰退していってしまうだろう。
以前に中国の「45万円EV」こと「宏光MINI EV」に乗る機会を頂いた。その際、多くのサプライヤーが「自社でこれくらいすぐに作れる」と仰っていたが、では誰が設計図を書くのか、という話になると皆さん沈黙してしまった。日本は完成車メーカーが強すぎるゆえに、下のレイヤーでコストダウンやカイゼンといった独自のモノづくりが発展を遂げた。しかし一方では、付加価値の高い設計・開発分野がおろそかになってしまった向きもある。
■人材育成と付加価値創出が鍵
幸いにも、10数年前まで強烈なライバル関係にあった国内メーカーも、現在は融和が進み協力関係にあるところも少なくない。この「横の繫がり」を縦にも活かしていくべきではないだろうか。かんたんに言えば、素材メーカーや部品メーカーなど様々なサプライヤーの若手エンジニアが、完成車メーカーに出向するなりして、一緒に研究開発するような仕組みができると良い。 こうした人的交流はサプライヤーだけではなく、今後の完成車メーカーの成長・発展を促す。クルマ作りにおける教育をいかに行っていくか、という視点が重要になるだろう。
クルマ作りにおいて様々な特許申請がなされているが、この申請内容を見ると各国のモノづくりの背景が見えてくる。日本メーカーは上流から下流に至るまであらゆる分野の特許を1社が申請するケースが多い。他方、欧州系のメーカーは分業が進んでおり、それぞれ自社の強みのある領域のみを申請しており、少ないリソースでも積極的な開発に注力できるメリットがある。中国もこの欧米型のモノづくりをしている。
一方、テスラのモノづくりは特殊で、テクニカルマネージャー(開発責任者)の思想に合ったモノをしっかり作る、というマネジメント体制が構築されている。欧米型より、むしろ一昔前の日本に近いモノづくりを行っているとも言える。しかし、テスラは「新しいものを取り入れた者が勝つ」である一方で、日本は「安全性が高く安くいいものを作れた者が勝つ」と、根本的な考え方に決定的な違いがある。
昨今の開発競争においては、日本が得意とする「安全性の担保」がないがしろにされつつあるのも事実だ。先日、現代自動車の「IONIQ5」が衝突後わずか数秒で車内に火の手が上がるという事故があった。欧州をはじめとしたマーケット攻略を急ぐばかりに、きちんとした安全性が担保されていなかった可能性も指摘されている。
しかし、今後のクルマ作りは自動運転の開発が加速しているよう、ハードよりソフトの部分での安全性確保が主流になりつつある。すなわち、衝突してからの安全性ではなく、そもそも衝突させない技術がフォーカスされている。
いまや運転免許を持っていない学生が自動車メーカーに就職し、開発を担う時代でもある。彼らにとってクルマ=運転ではなく、移動手段のひとつであり、今後は自動運転をベースとした開発が進んでいくだろう。クルマを運転せずに時間を活用できる、ということが付加価値となる。こうした付加価値の創出を後押しできれば、日本の勝ち筋のひとつとなるだろう。
(2022年6月25日号掲載)
